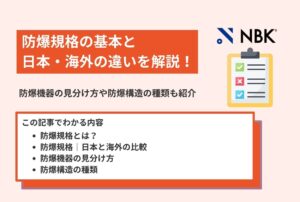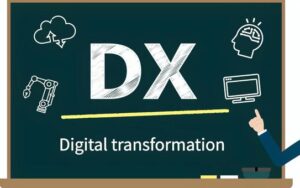爆発や火災のリスクがある化学工場や製油所、粉じんを扱う製造現場などでは、「防爆仕様」の機器や設備が欠かせません。
危険環境下での安全を確保するため、日本では「消防法」をはじめとする各種法律で厳格な規定が設けられています。特に、防爆エリアのゾーン区分や対応機器の選定は、事業者のリスクマネジメントに直結する重要な要素です。
本記事では、防爆仕様の基礎から関連法令、エリア区分、防爆機器の種類について解説します。防爆対策に関わるご担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
▼この記事でわかる内容
- 防爆仕様とは?
- 消防法との関係性
- 防爆エリアの危険箇所区分(ゾーン)
- 防爆機器の種類
- 消防法で定める危険物施設
NBKマーケティングでは、防爆エリア対応のスマートグラスやデバイス・タブレットPCを提供しています。
現場での情報確認や遠隔支援を可能にし、作業効率と安全性の向上に貢献します。耐久性や防爆性能に優れた設計で、過酷な環境にも対応可能です。
防爆対応の業務用デバイスをお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
当社サービスに関するご質問、お見積のお申し込みなど
お気軽にお問い合わせください
防爆仕様とは?消防法との関係性
防爆仕様とは、火災や爆発のリスクがある環境において、安全性を確保するための構造や設計のことです。可燃性物質と空気が混ざると爆発性雰囲気が生じ、火花などが引火源となると重大事故につながります。
そのため、消防法をはじめとする関連法令では、危険性のある区域における設備や機器に対して防爆仕様を求めています。特に消防法では、危険物施設の種類や構造、設置基準などを細かく定めており、事業者には適切な防爆対策が義務づけられています。
防爆構造を取り入れることで、事故リスクを抑え、法令遵守と現場の安全性の両立が可能です。安全確保と法令対応の両面で、防爆仕様と消防法の関係を理解しておきましょう。
防爆に関する法律
以下では、防爆に関する各法律がどのような場面で関係するのかを具体的に解説します。
▼防爆に関する法律
- 法律①|労働安全衛生法
- 法律②|電気事業法
- 法律③|消防法
法律①|労働安全衛生法
労働安全衛生法では、事業者に対して労働災害の防止措置を講じることを義務付けています。可燃性ガスや蒸気が存在する環境では、労働安全衛生規則第280条により、防爆構造を備えた機器の使用が求められます。
例えば、防爆電気機器を使用する際には、厚生労働大臣が定める「電気機械器具防爆構造規格」に適合していなければなりません。また、製造・設置には厚生労働省の登録検定機関による型式検定が必要です。
規定を怠ると、安全配慮義務違反や法令違反に問われ、民事・刑事の両面で責任を問われるリスクがあります。安全な作業環境を維持する上で、法令に即した機器選定と管理は欠かせません。
法律②|電気事業法
電気事業法では、電気設備の安全確保を目的として「電気設備に関する技術基準を定める省令」が制定されています。
危険場所における電気設備の工事や配線工事については、電気設備技術基準に基づいた適切な施工が求められます。ただし、防爆機器の型式検定や認証については労働安全衛生法の管轄であり、厚生労働省の登録検定機関による検定が必要です。
電気設備が技術基準に適合していない場合、電気事業法違反となり、使用停止命令や改修命令等の対象となるため注意しましょう。
法律③|消防法
消防法は、危険物の取扱いや貯蔵に関する規制を定めた法律で、防爆対応が必要となる場面でも適用されます。
例えば、危険物製造所や貯蔵所を新設・改修する場合、所轄の消防署への申請と使用前検査が必須です。設備が基準に適合していなければ、操業を開始できません。
また、消防法では火災予防の観点から、施設構造や電気設備の安全性にも厳しい基準が設けられています。防爆エリアを含む施設を計画する際には、事前に消防法上の要件を把握し、設計段階から適切な防爆対策を講じましょう。
防爆エリアの危険箇所区分(ゾーン)
防爆エリアは、可燃性ガスや蒸気、粉じんなどの発生頻度や滞留の可能性に応じて、いくつかのゾーンに区分されています。ここでは、防爆エリアにおける代表的な危険箇所の区分(ゾーン)について解説します。
▼防爆エリアの危険箇所
- 区分(ゾーン)
- ガス蒸気危険場所
- 粉じん危険場所
ガス蒸気危険場所
ガス蒸気危険場所とは、可燃性ガスや引火性のある蒸気が漏えい・滞留する恐れがあるエリアのことです。爆発性の雰囲気が形成されるため、電気設備や機器に対して防爆構造の採用が義務付けられています。
ガス蒸気危険場所は、発生頻度や滞留の程度に応じて、以下の3つのゾーンに区分されています。それぞれの特徴と防爆対策の要件を見ていきましょう。
▼ガス蒸気危険場所
- 特別危険箇所(0種場所・Zone0)
- 第一類危険箇所(1種場所・Zone1)
- 第二類危険箇所(2種場所・Zone2)
特別危険箇所(0種場所・Zone0)
Zone0は、爆発性雰囲気が常時または長時間にわたって存在するエリアです。可燃性ガスが液体から常に揮発しているタンク内部や、密閉容器の液面上部などが該当します。
Zone0では、わずかな点火源でも即座に爆発事故につながるため、最高レベルの防爆措置が求められます。機器の選定や設置にあたっては、Zone0対応の防爆規格を満たした製品の使用が必須です。
第一類危険箇所(1種場所・Zone1)
Zone1は、通常の運転や作業時に爆発性雰囲気が発生する可能性が高い区域を指します。
可燃性液体の入った容器の開口部や、点検時にガスが漏れる恐れのある設備周辺が典型例です。また、換気が不十分な室内ではガスが滞留しやすく、同様にリスクが高まります。
Zone1では、確実に防爆性能を持つ機器の導入と点検・保守によるガス漏れ防止が大切です。
なお、NBKマーケティングでは防爆エリア(ZONE1)対応スマートグラスを提供しております。
第二類危険箇所(2種場所・Zone2)
Zone2は、通常時には爆発性雰囲気が発生しないが、異常時に一時的に生成される可能性がある区域です。
バルブやパッキンの経年劣化によるガス漏れ箇所や、Zone1に隣接する空間などが該当します。爆発性雰囲気ができても短時間で拡散することが想定されるため、Zone0・1ほど厳格な要件ではありません。
ただし、万一の事態を想定した、簡易な防爆構造の採用や定期点検は必要です。
粉じん危険場所
粉じん危険場所とは、可燃性の粉じんが空気中に舞い、着火源と接触することで爆発の危険がある区域を指します。ガスとは異なり、微細な固体粒子が燃焼源となるため、異物の混入や掃除不足もリスク要因となります。
危険度に応じて以下の3段階に分かれているので、それぞれ確認していきましょう。
▼粉じん危険場所
- ゾーン20
- ゾーン21
- ゾーン22
ゾーン20
ゾーン20は、粉じん爆発の危険性が最も高い区域に指定されます。該当箇所は、サイロの内部や粉砕・乾燥工程で使用する密閉装置の内部などです。
ゾーン20では、機器の発熱や摩耗による火花でも爆発につながる可能性があるため、最高レベルの防爆構造が求められます。微粉末が常に存在することを前提とした機器選定と保守管理が不可欠です。
ゾーン21
ゾーン21は、通常の運転中に可燃性粉じんが空気中に断続的に存在する場所を指します。粉じんの投入や排出が行われる工程周辺、袋詰め作業を行うライン付近、清掃が不十分な通路や機器の周囲などが代表的です。
ゾーン20に比べて粉じんが常時浮遊しているわけではありませんが、作業や環境の変化によって発生しやすい区域です。そのため、一定の防爆性能を持つ設備と、定期的な清掃・点検による環境維持が重要になります。
ゾーン22
ゾーン22は、通常時に粉じんが空気中に存在しないか、ごく短時間しか存在しない区域です。設備が一時的に故障した際に漏れ出た粉じんが漂う場所や、ゾーン21に隣接する区域が該当します。
危険性は低いですが、万が一に備え簡易な防爆機器の導入が望まれます。
防爆機器の種類
ここでは、国内と海外それぞれの代表的な防爆規格について解説します。
▼防爆機器の種類
- 国内の規格
- 海外の規格
国内の規格
日本国内で使用される防爆機器には、主に以下の規格が適用されます。
- 電気機械器具防爆構造規格(構造規格)
- 工場電気設備防爆指針(整合指針)
構造規格は、昭和44年に制定され、改正を重ねながら運用されている従来の国内基準です。
一方、整合指針は国際基準に対応した技術指針で、よりグローバルな運用環境を想定して設計されています。どちらの規格も、厚生労働省が認可した登録検定機関(例:TIIS)による防爆型式検定への合格が必要です。
使用する機器がどの規格に基づいているかは、表示記号や合格証から確認できます。
海外の規格
海外で使用される防爆機器にも、各国や地域独自の認証規格があります。
代表的なものとして、IEC(国際電気標準会議)が運営する「IECEx」や、欧州連合の「ATEX指令」、米国の「UL規格」などが挙げられます。これらの規格を日本国内で使用する場合、国内規格に基づいた型式検定を受け直す必要があります。
消防法で定める危険物施設
消防法では、指定数量以上の危険物を取り扱う施設を「危険物施設」として定められており、以下の3つに区分されます。それぞれで必要な許可や安全対策、構造基準を確認しておきましょう。
▼消防法で定める危険物施設
- 施設①|危険物製造所
- 施設②|危険物貯蔵所
- 施設③|危険物取扱所
施設①|危険物製造所
危険物製造所は、可燃性液体やガスなどの危険物を製造・加工するために使用される施設です。指定数量以上の危険物を扱うため、爆発や火災のリスクが非常に高まります。
例えば、以下のような場所が該当します。
- アルコール類を原料とする薬品の精製工場
- スプレー缶へのガス充填ライン
製造所は、運用開始前に設置許可申請と使用前検査を受ける必要があり、操業後も定期的な点検と報告が義務づけられています。
施設②|危険物貯蔵所
危険物貯蔵所は、製造や取り扱いをせず、指定数量以上の危険物を一定期間保管しておくための施設です。石油やガソリンなどの燃料類を貯める地下タンクや屋外タンク、屋内に設けた容器保管エリアなどが該当します。
また、タンクローリーやコンテナでの移動・輸送を目的とした移動タンク貯蔵所も含まれます。施設の種類によって必要な構造や設備が異なるため、あらかじめ用途に応じた法的基準の確認が重要になります。
施設③|危険物取扱所
危険物取扱所は、危険物を一時的に扱う施設であり、製造は行わない点が製造所と異なります。消防法では、取扱所を以下のように4つに分類しています。
- 給油取扱所:ガソリンスタンド等
- 販売取扱所:容器入り危険物を販売する店舗
- 移送取扱所:配管やポンプで危険物を移送する施設
- 一般取扱所:上記以外で危険物を取り扱う施設
施設の性質上、作業員や一般利用者が直接危険物に接するため、安全表示や緊急時対応マニュアルの整備も重要です。
まとめ:防爆仕様と消防法を正しく理解して安全対策を進めよう
防爆仕様は、火災や爆発リスクのある現場における安全確保のために不可欠な対策です。消防法や関連法令では、防爆エリアの区分や設備要件、防爆機器の規格などを細かく定められています。
事故やトラブルを未然に防ぐには、法令を正しく理解し、現場環境に合った防爆対策を講じることが重要です。
NBKマーケティングでは、防爆エリア対応のスマートグラスや業務用タブレットPCを取り揃えています。過酷な現場でも安心して使える防爆仕様で、作業効率の大幅な向上と遠隔支援の実現をサポートします。
「安全性」と「生産性」を両立させたいご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。