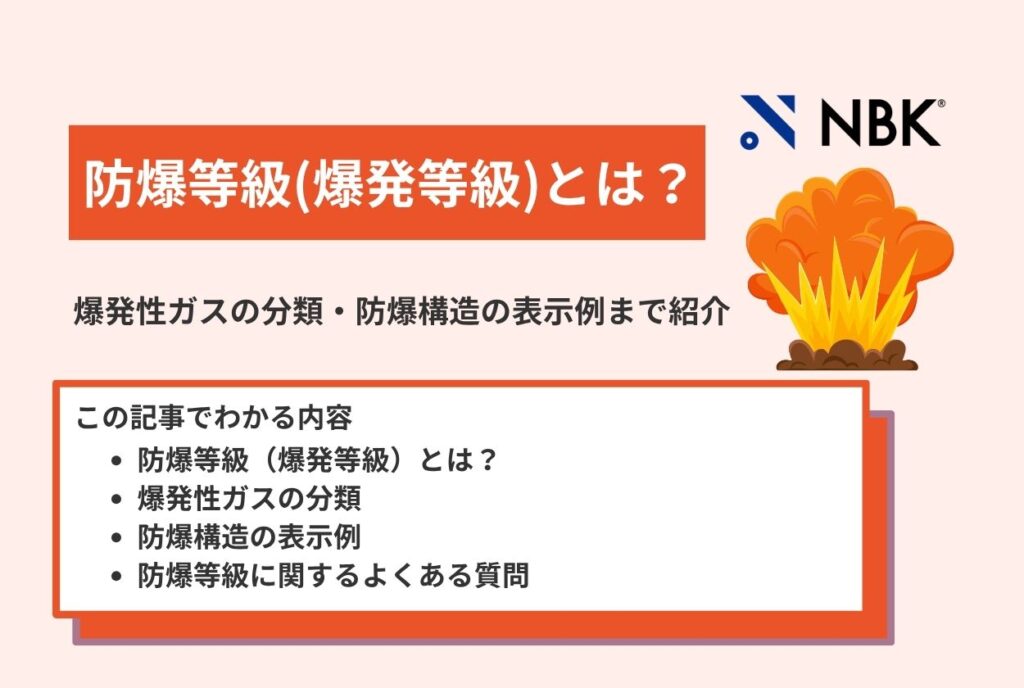
「防爆カメラやセンサーを導入したいけれど、防爆等級の意味がよく分からない」
「現場に合った防爆規格の選び方が分からず困っている」
このような悩みをお持ちではありませんか?
防爆等級とは、爆発の危険がある環境で使用する電気機器の安全性を示す重要な指標です。適切な防爆等級の機器を選ばなければ、重大な事故につながる恐れがあります。
本記事では、防爆等級の基本的な意味から、爆発性ガスの分類・防爆構造の表示例まで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、防爆等級の見方が理解でき、現場の危険度に応じた適切な防爆機器を自信を持って選定できるようになります。安全な設備運用のために、ぜひ最後までお読みください。
▼この記事を読んで分かること
- 防爆等級(爆発等級)とは?
- 爆発性ガスの分類
- 防爆構造の表示例
- 防爆等級に関するよくある質問
NBKマーケティングでは、完全無線型防爆IoTカメラ(LC-EX10)を取り扱っています。
Zone 2対応で、すべての危険特性のガス蒸気環境に設置が可能なカメラです。気になる方はぜひ、以下より詳細をご確認ください。
防爆等級(爆発等級)とは?

防爆等級(爆発等級)は、爆発性ガスがどれだけ危険かを示す分類基準のことです。具体的には、ガスの最大安全すきま「火炎逸走限界」といった数値に基づいて決められています。
最大安全すきまは、電気機器内部で爆発が発生した際、どの程度の隙間があれば外部に火炎が伝わらないかを表す数値です。
例えば、水素のように火炎が狭い隙間でも伝わりやすいガスは危険度が高く、プロパンのような一般的なガスは比較的危険度が低いと判断されます。
防爆等級を理解することで、現場で扱うガスの危険性を正確に把握でき、適切な防爆機器の選定が可能になります。
爆発性ガスは、日本の防爆規格と国際規格で分類基準が異なるため、以下で順に説明します。
爆発性ガスの分類

爆発性ガスは、日本の構造規格と国際構造規格に分類されています。なお、防爆規格(爆発規格)は、日本で定められている「電気機械器具防爆構造規格」に基づく分類指標の1つです。
それぞれの規格について確認していきましょう。
▼爆発性ガスの分類
- 分類①|電気機械器具防爆構造規格(防爆等級と発火度)
- 分類②|国際電気基準会議の国際規格(グループと温度等級)
分類①|電気機械器具防爆構造規格(防爆等級と発火度)
電気機械器具防爆構造規格では、防爆電気機器の対象となる爆発性ガスを火炎の伝わりやすさに基づいて3段階の爆発等級に分類しています。
また、発火温度によって5段階に区分し、それぞれのガス種に安全に対応できる防爆電気機器の性能を規定しています。
それぞれをまとめたのが以下の表です。
| 爆発等級/発火度 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ・アセトン ・アンモニア ・一酸化炭素 ・エタン ・酢酸 ・トルエン ・ベンゼン ・メタん | ・エタノール ・酢酸イソぺンチル ・酢酸エチル ・1-ブタノール ・ブタン ・プロパン ・無水酢酸 ・メタノール | ・ガソリン ・ヘキサン | ・アセトアルデヒド ・ジエチルエーテル | |
| 2 | ・石炭ガス | ・エチレン ・エチレンオキシド | |||
| 3 | ・水性ガス ・水素 | ・アセチレン | 二硫化炭素 |
引用:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006)
防爆電気機器には「d2G3」のような記号が表示されており、これは防爆等級2以下、発火度G3以下のガス環境で使用可能という意味です。
つまり、表示された数値と同じか、それより小さい数値のガス環境であれば安全に使用できることが保証されています。このような表示方法により、現場の作業者は機器の適合性を簡単に判断でき、適切な防爆機器の選定が可能です。
防爆等級(爆発等級)と発火度の分類表についても確認していきましょう。
防爆等級(爆発等級)の分類表
防爆等級(爆発等級)の分類表は以下の通りです。
| 爆発等級 | 火炎逸走限界の値(mm) |
|---|---|
| 1 | 0.6 を超えるもの |
| 2 | 0.4 を超え0.6 以下のもの |
| 3 | 0.4 以下 |
引用:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006)
爆発等級は、可燃性ガスがどの程度の隙間を通して火炎が伝わるかを示す指標です。
特に「等級3」は火炎逸走限界が小さいため、わずかな隙間からでも火炎が通過しやすく、防爆構造の設計において最も厳しい基準が求められます。
現場で使用される防爆機器は、対象となるガスの爆発等級を正確に把握したうえで選定・設置しましょう。
発火度の分類表
発火度の分類表も以下にまとめましたので、ご確認ください。
| 爆発性ガスの発火温度(℃) | 発火度 | 電気機器の許容温度(℃) |
|---|---|---|
| 450を超えるもの | G1 | 360 |
| 300を超え450以下のもの | G2 | 240 |
| 200を超え300以下のもの | G3 | 160 |
| 135を超え200以下のもの | G4 | 110 |
| 100を超え135以下のもの | G5 | 80 |
引用:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006)
発火度は、爆発性ガスや蒸気が自然に着火する温度に基づいて分類される指標です。値が低いほど、より低い温度で着火しやすく、危険性が高いガスであることを示します。
防爆電気機器では、内部で発生する熱が周囲の可燃性ガスを発火させないよう、発火度に応じた許容温度が定められています。
分類②|国際電気基準会議の国際規格(グループと温度等級)
国際電気基準会議(IEC)の規格では、爆発性ガスを「グループ」と「温度等級」で分類しています。
| グループ/温度等級 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| IIA | ・アセトン ・アンモニア ・酢酸エチルトルエン ・ベンゼン ・エタン ・メタン ・酢酸 ・1- ブタン | ・1- ブタノール ・無水酢酸 ・プロパン ・メタノール ・n - ブタン | ・n - ヘキサン | ・アセトアルデヒド | ||
| IIB | ・一酸化炭素 | ・エタノール ・エチレン ・エチレンオキシド | ・ジエチルエーテル | |||
| IIC | ・水素 | ・アセチレン | ・二硫化炭素 |
引用:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006)
グループ分類では、一般的な工場や事業場で使用される防爆機器を「グループⅡ」として、さらにⅡA、ⅡB、ⅡCの3つに細分化します。
ⅡAが最も危険度が低く、ⅡCが最も高い分類です。グループⅡの防爆機器は、耐圧防爆構造や本質安全防爆構造の特性に応じて、さらに細分化されています。
温度等級は、T1からT6までの6段階で表され、数字が大きいほど低い温度で発火する危険なガスに対応します。
T6等級の機器は最高表面温度が85℃以下に抑えられており、二硫化炭素のような低温で発火するガスにも対応可能です。
国際規格は世界各国で採用されているため、輸入機器や海外プラントでの作業時には、分類方法の理解が不可欠です。
グループの分類表
上記で解説した通り、グループの分類では、耐圧防爆構造と本質安全防爆構造の特性に応じて細かく分類されているので確認していきましょう。
| 耐圧防爆構造の電気機器分類 | 最大安全隙間の値(mm) |
|---|---|
| ⅡA | 0.9 以上 |
| ⅡB | 0.5 を超え0.9 未満 |
| ⅡC | 0.5 以下 |
引用:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006)
| 耐圧防爆構造の電気機器分類 | 最小点火電流比(メタン=1) |
|---|---|
| ⅡA | 0.8 を超えるもの |
| ⅡB | 0.45 を超え0.8 以下のもの |
| ⅡC | 0.45 以下 |
引用:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006)
なお、IEC規格では、防爆機器を用途別に「グループⅠ(炭鉱用)」「Ⅱ(ガス・蒸気用)」「Ⅲ(粉じん用)」の3区分に分類されています。
温度等級の分類表
温度等級とは、電気機器の表面温度が周囲の可燃性ガスの発火温度を超えないように区分した基準です。温度等級の分類表を以下にまとめましたので、ご確認ください。
| 電気機器の最高表面温度(℃) | 温度等級 | 爆発性ガスの発火温度(℃) |
|---|---|---|
| 450 | T1 | 450を超えるもの |
| 300 | T2 | 300を超えるもの |
| 200 | T3 | 200を超えるもの |
| 135 | T4 | 135を超えるもの |
| 100 | T5 | 100を超えるもの |
| 85 | T6 | 85 を超えるもの |
引用:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006)
温度等級を確認し、対象ガスの発火温度に適合した防爆機器を正しく選定しましょう。
防爆構造の表示例

ここでは、電気機械器具防爆構造規格と国際電気基準会議の国際規格に基づく記号の表示例を紹介します。それぞれの意味を一つひとつ解説しているので、ぜひ参考にしてください。
▼防爆構造の表示例
- 表示例①|電気機械器具防爆構造規格に基づく記号
- 表示例②|国際電気基準会議の国際規格に基づく記号
表示例①|電気機械器具防爆構造規格
まずは、電気機械器具防爆構造規格でよくある表示例「d2G4」と「eG3」の読み取り方について解説します。「d2G4」の読み取り方は以下の通りです。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| d | 耐圧防爆構造 |
| 2 | 爆発等級2:火炎逸走限界の値(0.4mm 以上0.6mm 以下) |
| G4 | 発火度G4:自然発火温度が280℃超~450℃以下 |
「eG3」の読み取り方も確認していきましょう。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| e | 安全増防爆構造 |
| G3 | 発火度G3:自然発火温度が135℃超~280℃以下 |
わかりにくい数字の羅列に見えても、一つひとつの記号には明確な意味があります。防爆構造の種類や詳細な分類については、以下の記事でより詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
>>防爆規格の基本と日本・海外の違いを解説!防爆機器の見分け方や防爆構造の種類も紹介
表示例②|国際電気基準会議の国際規格
次に、国際電気基準会議の国際規格に基づく表示例も見てきます。今回は、完全無線型IoTカメラ LC-EX10の防爆記号「Ex ic IIC T6 Gc」を例に見ていきましょう。
それぞれの記号が何を示しているのか、表にまとめましたのでご確認ください。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| Ex | IECに基づく防爆記号 |
| ic | 本質安全防爆構造レベルc:1つの故障状態で安全性を確保 |
| IIC | グループIIC:最も危険なガス(水素、アセチレン、二硫化炭素等) |
| T6 | 温度クラス6:機器表面最高温度85℃以下 |
| Gc | Zone 2のみ使用可、Zone 0・1では使用不可 |
防爆記号を正しく理解することで、機器が対応できる危険場所やガスの種類、安全性能レベルを正確に把握できるようになります。
防爆等級に関するよくある質問

最後に、防爆等級に関するよくある質問2つに回答しています。防爆機器の導入や選定に不安がある方は、ぜひ最後までお読みください。
▼防爆等級に関するよくある質問
- 質問①|防爆等級(爆発等級)が高いほど安全ですか?
- 質問②|防爆等級(爆発等級)はどのように確認できますか?
質問①|防爆等級(爆発等級)が高いほど安全ですか?
防爆等級(爆発等級)は、数字が大きいほど危険性が高いことを示します。つまり「爆発等級3」が最も危険なガスを対象とする等級です。
爆発等級は、火炎逸走限界(火炎が通過できる最小の隙間)によって分類されます。火炎逸走限界が小さいほど、より微細な隙間から火炎が漏れやすく、爆発を防ぐのが難しくなります。
そのため、爆発等級3(0.4mm以下)は最も厳しい構造が必要です。
質問②|防爆等級(爆発等級)はどのように確認できますか?
防爆等級は防爆機器の銘板や型式検定合格証で確認できます。商品ページには、大抵「標準仕様」が掲載されているので、ぜひご確認ください。
まとめ:防爆等級を正しく理解して環境に合った製品を選ぼう

防爆等級(爆発等級)は、爆発性ガスの危険度を示す重要な分類基準です。
日本の電気機械器具防爆構造規格では「防爆等級(爆発等級)」と「発火度」で分類されています。また、国際規格では「グループ」と「温度等級」の分類です。
機器に表示された記号は、対応可能なガスの種類や危険度を示しており、現場の環境に応じて正しく読み取ることが大切です。
本記事で解説した分類表や表示例を参考に、現場で扱うガスの特性を正確に把握し、適切な防爆機器を選定しましょう。

