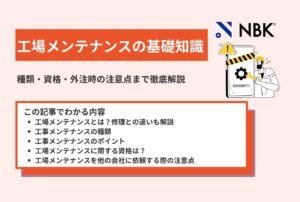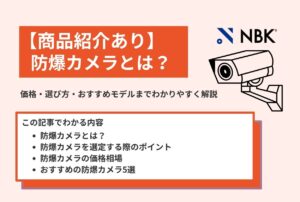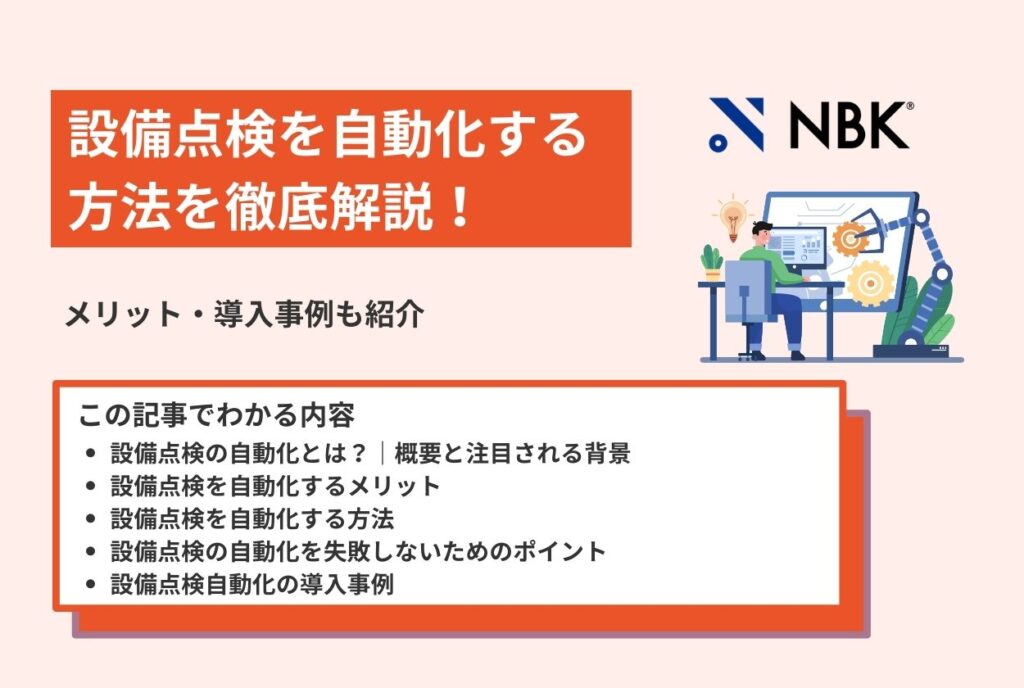
工場やプラント、オフィスビルなどでは、設備点検の自動化が進みつつあります。従来の点検業務は、広大な敷地を人が巡回し、アナログ計器を目視確認する方法が主流でした。
しかし、人的リソース不足や高齢化、安全リスクの増大といった課題から、従来の点検だけでは限界が見え始めています。
そこで注目されているのが、ロボットやIoTセンサー、AIを活用した自動化です。自動化によって人的負担を軽減し、安全性や精度を高めながら、コスト削減や生産性向上を同時に実現できます。
本記事では、設備点検を自動化するメリットや導入方法、失敗しないためのポイント、さらに実際の導入事例まで紹介します。ぜひ、最後までお読みください。
▼この記事を読んで分かること
- 設備点検の自動化とは?|概要と注目される背景
- 設備点検を自動化するメリット
- 設備点検を自動化する方法
- 設備点検の自動化を失敗しないためのポイント
- 設備点検自動化の導入事例
設備点検の自動化をお考えの方は、NBKマーケティングにご相談ください。
NBKマーケティングでは、ugo株式会社の日常巡回点検を自動化する自律型走行ロボット「ugo mini」を提供しています。狭い通路や静粛性が求められる環境でも稼働し、24時間無人で巡回・監視を実現します。
詳細は以下からご確認ください。
設備点検の自動化とは?|概要と注目される背景

設備点検の自動化とは、人が行っていた状態確認や異常検知を、IoTやAI、ロボットの技術を活用して自動化する仕組みです。圧力計や温度計の読み取りから、振動や音の変化の検知まで、幅広い作業をデジタル化します。
設備点検の自動化が注目されているのは、設備の老朽化による故障リスクの増大と、保全担当者の人手不足といった課題があるためです。特に製造業では、熟練技術者の高齢化が進む一方で、若手人材の確保が困難な状況が続いています。
加えて、工場内に点在する数百〜数千の計器を巡回点検するのは、時間・体力ともに大きな負担です。自動化により点検頻度を上げながらも人的負担を軽減し、設備の安定稼働と生産性向上の両立を実現できます。
設備点検を自動化するメリット

設備点検の自動化は、製造現場が抱えるさまざまな課題を解決する有効な手段です。ここでは、設備点検の自動化がもたらす5つのメリットについて詳しく解説していきます。
▼設備点検を自動化するメリット
- メリット①|コストを削減できる
- メリット②|安全に点検できる
- メリット③|リアルタイムで情報共有できる
- メリット④|人的ミスを防げる
- メリット⑤|業務効率・生産性が向上する
メリット①|コストを削減できる
設備点検の自動化により、人件費を中心とした運用コストを削減できます。
従来の巡回点検は、数百箇所の計器を確認するため膨大な工数がかかっていました。IoTセンサーや画像認識技術を導入すれば、点検要員をほかの業務に配置転換できます。
また、紙ベースの点検記録をデジタル化することで、データ入力や書類管理にかかる間接的なコストも削減可能です。点検データが自動的にシステムに蓄積されるため、報告書作成や承認プロセスも効率化できます。
初期投資は必要ですが、長期的には人件費削減効果により投資回収が見込めます。
メリット②|安全に点検できる
自動化により危険作業を人が担う必要がなくなり、労働災害の可能性を抑えられます。例えば、以下のようなシステムを導入することで、危険エリアに人が立ち入ることなく点検作業できます。
- ドローン
- 自律走行ロボット
- 遠隔監視センサー
センサーによる24時間監視体制を構築すれば、異常の兆候を早期に検知し、大規模な事故を未然に防ぐことも可能です。設備点検の自動化は安全文化の醸成にも大きく貢献します。
メリット③|リアルタイムで情報共有できる
点検データのデジタル化により、現場の状況を管理部門や保全チームがリアルタイムで把握できるのも大きなメリットです。従来の紙ベースの点検では、現場から事務所への報告に時間差が生じ、異常への対応が遅れるケースがありました。
クラウドシステムと連携した自動点検システムを導入すれば、異常値を検知した瞬間に関係者へアラートを発信し、迅速な対応が可能です。
また、複数拠点の設備状況を一元管理できるため、工場間での横断的な分析や改善活動も促進されます。スマホやタブレットで点検結果を共有すれば、管理者は遠隔から指示でき、判断スピードも向上します。
メリット④|人的ミスを防げる
自動化システムは設定されたルールに従って確実に点検を実施するため、見落としや記録ミスといった人為的エラーを排除できます。作業員の体調や経験値、集中力の違いによる点検品質のばらつきもなくなり、常に一定水準の点検精度を維持できます。
アナログメーターの読み取り値も画像認識により正確にデジタル化され、転記ミスや計算間違いも発生しません。蓄積された正確なデータを分析することで、設備の劣化傾向や故障パターンを把握でき、予防保全の精度も向上します。
属人化していた点検ノウハウをシステムに組み込むことで、技術継承の課題も解決されます。
メリット⑤|業務効率・生産性が向上する
点検作業の自動化により、現場の効率が大幅に向上し、工場全体の生産性も高まります。
自動収集されたデータを分析することで、点検ルートの無駄を省き、点検頻度を最適化できるからです。
設備の稼働データと点検結果を組み合わせた分析により、予知保全の精度が高まり、計画外の設備停止を削減できます。結果的に作業員は設備改善や品質向上といった、より価値の高い業務に注力できるようになります。
設備点検を自動化する方法
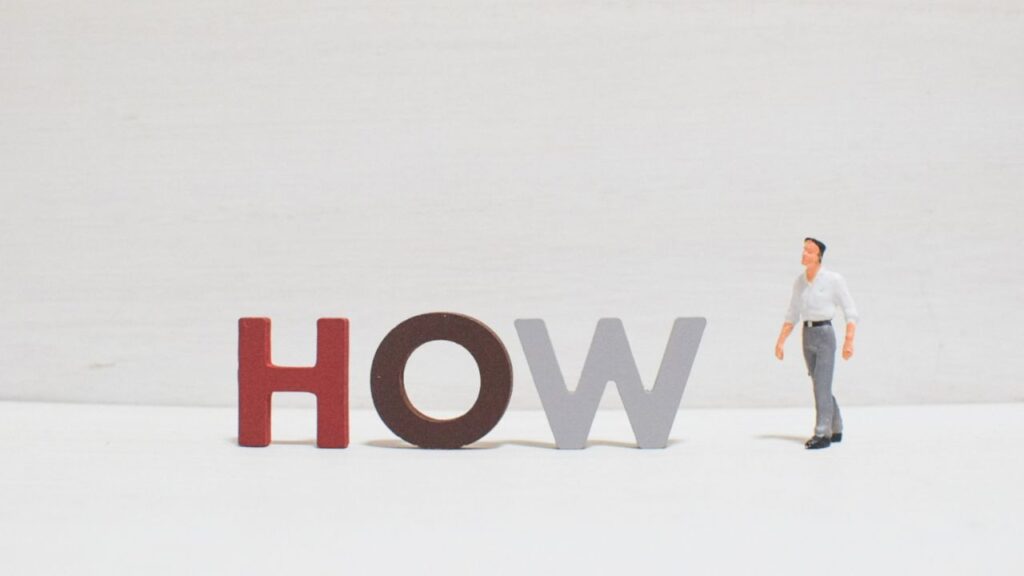
ここでは設備点検の3つの自動化方法について、具体的な導入イメージと活用例を紹介します。
▼設備点検を自動化する方法
- 方法①|ロボットを導入する
- 方法②|AIやIoT技術を取り入れる
- 方法③|センサー機器を活用する
方法①|ロボットを導入する
点検用ロボットの導入により、人が立ち入れない危険箇所や広大なエリアの点検を自動化できます。例えば、以下のようなロボットが設備点検の自動化に有効です。
- ドローン
- 自律走行型ロボット
空中から点検するドローンは、送電線や煙突、大型タンクの外壁など、高所作業が必要な設備の点検に威力を発揮します。4Kカメラや赤外線カメラを搭載したドローンなら、目視では発見困難な微細なクラックや腐食も検出可能です。
一方、地上を移動する自律走行ロボットは、プラント内の巡回点検に適しています。配管が入り組んだ狭隘部や、高温・有毒ガスが発生する環境でも、事前にプログラムされたルートに沿って確実に点検を実施します。
NBKマーケティングでは、ugo株式会社の自律型走行ロボットやHibot社の多関節ロボットを提供しているので、詳しくは以下をご確認ください。
方法②|AIやIoT技術を取り入れる
AIとIoTを組み合わせることで、設備の状態を常時監視し、異常の予兆を自動的に検知するスマートな点検システムを構築できます。画像認識AIを活用すれば、アナログメーターの数値を自動で読み取り、デジタルデータとして記録することも可能です。
過去の故障データを学習したAIは、設備ごとの故障パターンを把握し、「あと何日で部品交換が必要」といった予測も提示してくれます。初期設定には専門知識が必要ですが、一度システムを構築すれば、経験の浅い作業員でも高度な予知保全を実現できます。
NBKマーケティングの計器読取AI、LiLz Gaugeを活用すれば、点検と記録作業を軽減できるので、効率化をお考えの方はぜひご相談ください。
LiLz Gaugeに関するご質問、お見積り、試験導入のお申し込みなど
お気軽にお問い合わせください
方法③|センサー機器を活用する
各種センサーの設置は、比較的低コストで始められる自動化の第一歩として多くの工場で採用されています。振動センサーをモーターやポンプに取り付ければ、ベアリングの摩耗や軸のずれを振動パターンの変化から検知できます。
近年では、無線通信機能を持つワイヤレスセンサーが普及し、配線工事なしで既存設備への後付けが可能になりました。圧力変動や異常音を監視するなど、センサーを用途に合わせて使い分けられます。
段階的に導入範囲を拡大できるため、予算に応じた柔軟な自動化計画を立てやすいメリットがあります。
NBKマーケティングでは、LiLz株式会社の完全無線型サーモカメラを提供しているので、導入をご希望の方はご相談ください。
設備点検の自動化を失敗しないためのポイント
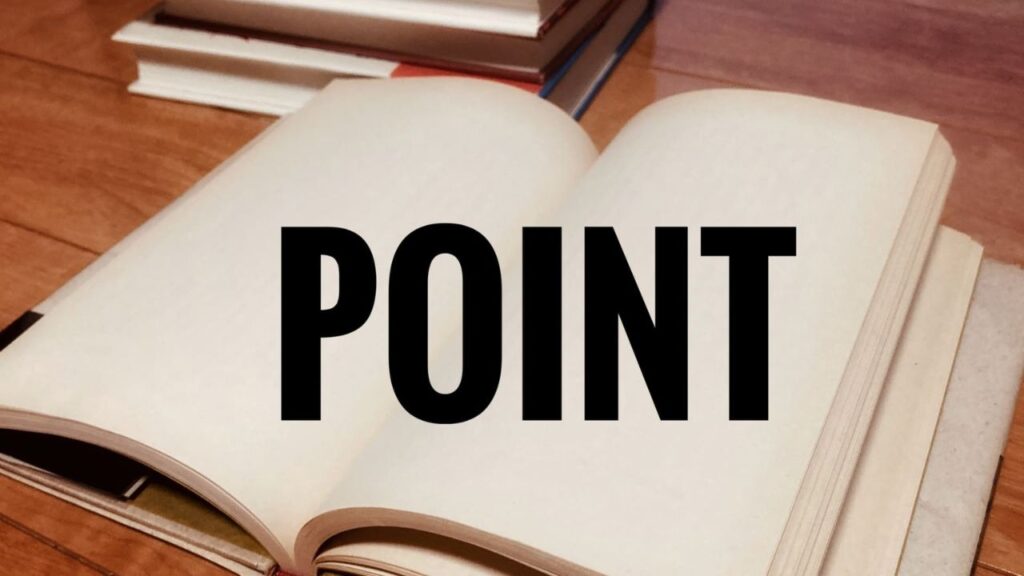
設備点検の自動化は大きなメリットをもたらしますが、導入方法を誤ると期待した効果が得られず、投資が無駄になるリスクもあります。ここでは、多くの企業が陥りがちな失敗を回避し、着実に自動化を進めるためのポイントを解説します。
▼設備点検の自動化を失敗しないためのポイント
- ポイント①|自動化の目的と対象範囲を整理する
- ポイント②|現場で運用しやすい機材とソフトを導入する
ポイント①|自動化の目的と対象範囲を整理する
自動化を成功させるには「何のために導入するのか」という目的を明確にし、段階的に導入範囲を拡大することが不可欠です。「最新技術だから」という理由だけで導入すると、現場が混乱し、高額な投資が無駄になってしまいます。
まずは「点検時間を30%削減する」「危険箇所の点検を100%無人化する」といった具体的な数値目標を設定するところから始めましょう。
また、導入範囲を最初から全体に広げるのではなく、成果が期待できる部分から段階的に進めることが望ましいです。例えば、アクセスが困難な高所の設備や点検頻度が高い重要設備など、自動化の恩恵を受けやすい箇所を選定します。
目的と範囲を明確にすることで、必要な機能や精度も自ずと決まり、過剰な投資を避けながら確実な成果を上げられます。
ポイント②|現場で運用しやすい機材とソフトを導入する
高機能で複雑なシステムよりも、現場作業員が直感的に操作できるシンプルな機材を選ぶことが、安定した運用を支えるポイントです。日常的に使い慣れたデバイスを活用することで、導入のハードルを大幅に下げられます。
例えば以下のような機材・システムを導入しましょう。
- タブレット端末で操作できる簡易型の点検システム
- スマートフォンアプリと連携したセンサー
ソフトウェアについても、クラウド型のサービスを選択すれば、高額なサーバー投資や専門的なIT知識なしに運用を開始できます。現場の声を反映しながら、まずは最低限の機能でスタートし、段階的に拡張していくことで導入の成功につながります。
設備点検自動化の導入事例

最後に、NBKマーケティングがご支援させていただいた事例を紹介します。
株式会社ヤクルトでは、CEタンクの目視点検を効率化するため、計器読取AI「LiLz Gauge」を導入しました。
従来は1日3回、人の手による確認が必要でしたが、リモートで監視できるようになり、移動や作業にかかる時間を大幅に短縮。さらに、ガス補充のタイミングを把握できるようになったことで、業務の透明性向上にもつながっています。
導入にあたっては、スターターキットを利用して検証を実施。設置場所や光の影響といった課題を把握し、本格導入後には安定したデータ取得が可能になりました。
株式会社ヤクルトでは、今後は配線工事が難しい設備への展開も視野に入れられており、幅広い分野での活用が期待されます。
以下の記事で導入効果について詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。
まとめ|設備点検の自動化で効率化とコスト削減を実現しよう
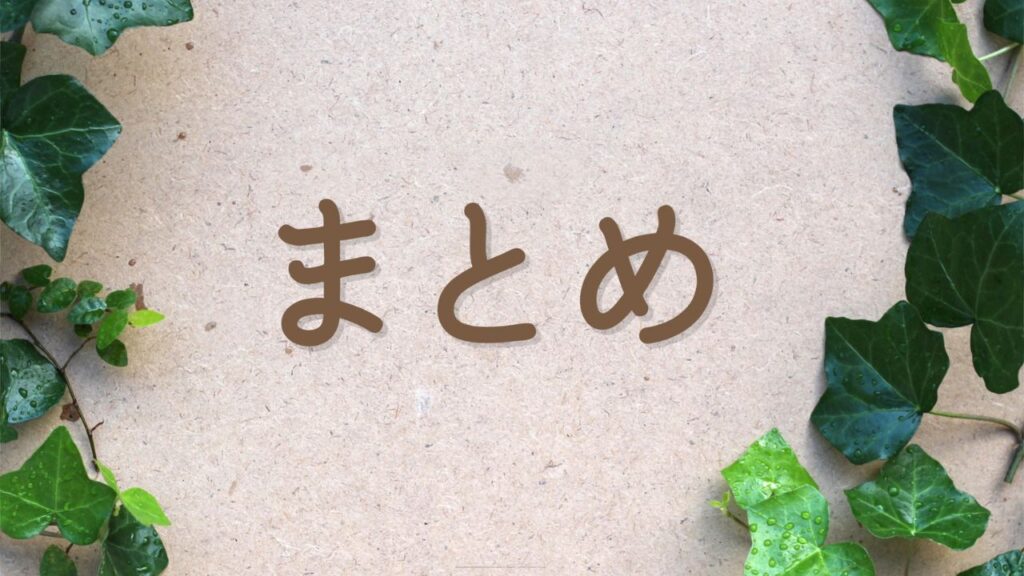
設備点検の自動化は、労働力不足や安全リスクの増大といった課題を解決し、生産性とコスト削減を同時に実現する有効な手段です。ロボットやIoT、AIを活用すれば、危険作業の無人化や点検精度の均一化、リアルタイム情報共有ができます。
自動化する際には、目的や対象範囲を明確にし、現場で運用しやすいシステムを選ぶことが大切です。ぜひ本記事を参考に、設備点検の自動化で効率化とコスト削減を実現しましょう。
NBKマーケティングでは、設備点検の自動化に関するご相談を受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。